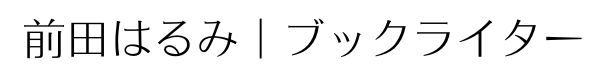ライターとして歩んできた道のりをふり返ります。
幼少期~学生時代:ライターとしての萌芽
子どもの頃から「書く」ことが好きでした。それを将来の仕事として意識し始めたのは、高校生の頃です。報道の仕事に憧れて、よく眺めていたのは「LIFE」などの報道写真集。一枚の写真がダイレクトに伝えてくるものに胸を打たれ、「言葉をどれだけ並べても写真にはかなわないかもしれない」と思う一方で、「それでも私は、文章でこの世界のことを伝えたい」と心に決めました。出来事の背景にある人々の思いや、その時代の空気までも文章で描きたい——その思いは、この頃すでに芽吹いていたのだと思います。
大学卒業後、ジャーナリズムを学ぶためアメリカの大学院へ。初めてのライティング課題は、「街で取材したことを記事にする」というものでした。クラスメイトたちが次々と街ゆく人に声をかけるのを横目に、英語に不慣れな私は立ちすくむばかり。残り時間が迫るなか、飛び込んだのは近くのコンビニでした。耳を澄ませば聞こえてくる、レジの音、客と店員の会話……。観察したことをそのまま記事にすると、意外にも「その場にいるかのような臨場感がいい」と好評でした。これがライターとして初めて感じた手ごたえであり、「世界観を伝える」という私の文章スタイルの原点です。
1996年~2005年:会社員を経て、ライターとなる
帰国後、新聞記者を目指すも叶わず、広報代理店に入社。その後、マーケティング企画制作会社を経て、2004年にフリーランスライターとして独立しました。宣伝会議が主催する編集・ライター養成講座を受講し、同社が発行する『編集会議』『販促会議』などの雑誌でアルバイト的に記事を書き始めます。これがライターとしてのスタートでした。
4分の1ページのコラムから始まり、少しずつ任されるページ数が増えていきました。『編集会議』では雑誌や書籍の編集者にヒットの秘訣を取材し、『販促会議』では企業の販促事例を記事にしました。当時の私にとって、収入は「一文字一文字を書き連ねた血と汗の結晶」。身を削るように書き続けた経験が、今の土台になっています。『編集会議』の取材を通じて編集者の方々と仕事につながるご縁を得られたことや、『販促会議』で会社員時代の経験を生かせたことは、ふり返れば幸運だったと思います。
2006年~2008年:媒体としての役割に目覚める
駆け出しの頃は、取材で聞いたことをそのまま書いていた気がします。そんなとき、取材相手から言われたのが、「確かにそう言ったけど、でもなあ」というひと言。言葉どおりに書くだけでは、伝わらないことがあると気づかされた出来事でした。
取材時には、うまく言葉にできないこともあります。その人が本当に伝えたかったことは何なのか、それを丁寧にくみ取りつつ、こちらでも事実を確認して、必要なら言葉を補足して読者が理解できる形にする。それがライターの仕事だと理解しました。もちろん、言っていないことを勝手に創作しないというルールは守ります。そうやって書いた記事が読者に届き、取材相手からも「これが伝えたかった」と喜んでもらえるとライター冥利に尽きます。この頃から私は、「誰かの言葉をより伝わる形にする媒体」と自分のことを意識するようになりました。
2009年~2015年:初の書籍編集協力、そして10年目の挫折
初めて商業出版のブックライティングを担当したのは『プレイフル・シンキング』(上田信行著、宣伝会議)。「話されたことをそのまま書くのではなく、意図をくみ取って文章にする」という雑誌での経験は、本づくりでも役立ちました。この頃に取材を通して出会った著者の方とは、10冊の本を一緒につくる機会に恵まれました。一人の著者の方とこれだけ長く仕事をご一緒できたことをとても光栄に思っています。本と並行して雑誌の仕事も増え、『THE21』(PHP研究所)では多くの経営者やビジネスパーソンに取材し、働き方やマネジメント、仕事術などの記事を執筆しました。
転機を挙げるとするなら、ライター10年目で経験した挫折でしょうか。ある本の仕事で、「これ、ちゃんと理解して書いていますか? ロジックが飛んでますよ」と編集者の方から指摘され、赤字が何度も返ってきました。結局、私はその仕事をまっとうできず、途中でお役御免に。期待にこたえられない自分が情けなく、悔しい思いをしましたが、自分の至らなさを率直に教えていただいたことは感謝しています。それ以来、「自分でとことん理解してから書く」ことが私の鉄則となり、よりわかりやすい文章を書く力につながっています。
2016年~2022年:伝えたいテーマにめぐりあう
2018年、初の自著『トップも知らない星野リゾート』(PHP研究所)を出版しました。『THE21』で担当した「星野リゾートの現場力」という連載記事を書籍化したのがこの本です。当時はまだ珍しかった“フラットな組織文化”。社内の役割や階層に関係なく自由にものが言えて挑戦できる職場環境が日本企業に広がっていけば、働く人にとっても組織にとっても幸せなのではないか。そんな思いで取材執筆しました。「生き生きと働く」「自分らしく働く」というテーマは、この頃から私自身の関心事であり、ライターとしての軸のひとつになりました。
そのころ編集協力で携わった『PLAYWORK』(ピョートル・フェリクス・グジバチ著、PHP研究所)も同様に、「遊ぶように働く」という概念が一般的ではなかった時代に、どうすれば読者に興味を持ってもらえるかを試行錯誤しながらつくりました。挑戦したのは、「遊ぶように働く」を例示するエピソードを散りばめながら、PLAYWORKの世界観を提示することです。通常、本の構成は編集者と著者で固めていきますが、この本ではライターの私に構成から任せていただけたことも、大きな自信となりました。
2023年~現在:共創による本づくりと、これからの挑戦
これまでは編集者からの依頼が仕事のスタートでしたが、2025年刊行の『心を病む力』(上谷実礼著、東洋経済新報社)は、著者の方と共に企画を練り、出版社に提案して実現したものです。著者の「社会のなかで自分らしく生きる」という姿勢に共感し、そのメッセージを広く読者に届けたいと思ったのがきっかけです。著者・編集者の方々と何度も打ち合わせを重ね、チームでつくり上げました。思い入れの深い一冊です。
これらの経験を糧に、これからも自分の関心や得意を生かしながら、読者に届く言葉を丁寧に紡いでいきたいと考えています。編集者や著者の方々との信頼関係を大切にしながら、読者の心に残り、人生を変えるきっかけになるような本づくりをサポートしていきます。
ライティングに関することならお気軽にご相談ください。